日本のものづくりを支えてきた伝統的な匠の技と最先端のものづくり技術が集結した、「ものづくり匠の技の祭典2025」。今回は、さまざまな分野の匠たちが実演を通じて卓越した技を披露したスペシャルステージの様子を紹介するね。

わざねこ、大興奮!マグロ解体ショー〜調理の匠ステージ
この日、わざねこがいちばん楽しみにしていたのは、一般社団法人東京都日本調理技能士会による「国産天然マグロ解体ショー」だよ。調理の匠たちが大マグロを、目の前で解体する圧巻のパフォーマンス。マグロ大好物のわざねこには、たまらんにゃ。この日、披露されたのは、高知県の南に位置する柏島沖で定置網にかかった75キロのマグロ。船で網を引きながら、そのまま養殖場に運び、数カ月間育ててから、電気銛(もり)で瞬間的に〆たものだよ。この大物を、調理の匠たちが3人がかりで解体していくんだ。

刀みたいな包丁!
使うのは、長さ約1m30cmの包丁!こんな刀みたいな包丁、初めて見たよ。頭部とヒレを落としたら、お腹にあるギザギザの小離鰭(しょうりき)という部分をそぎ落とし、切れ込みを入れるよ。次に背骨に沿って左右の身と中骨の3つの部位に切り分け、いわゆる「三枚おろし」にするんだ。それぞれの身を背肉と腹肉に分け、四つ割に。身の色が濃い三角形の部分が赤身、腹身側にあるのが中トロ、大トロだよ。断面はとてもきれい。脂がのって旨そうだにゃー。皮や血合い、腹骨、背骨を丁寧に取り除き、「柵取り(さくどり)」して調理しやすいかたちに整えるよ。黒っぽい血合い部分も空気に触れると、次第に赤みが増していくんだ。栄養豊富で、下処理すれば美味しく食べられるよ。腹骨や背骨についた身も、こそげ取って食べると美味しいんだ。そして、1本のマグロから2つしか取れない希少な部位が、「カマトロ」だよ。エラの後ろの「カマ」の内側に詰まった肉で、特に脂がのって、美味しい部位なんだ。
海外では、マグロを輪切りにするそうだけど、日本では丁寧に解体し、部位ごとに適した調理法を工夫するよ。マグロは骨以外、ほとんど捨てるところがないんだ。包丁で丁寧に捌いていく匠の技に、日本の魚文化の奥深さを感じたよ。

掛布団の歴史を辿って〜寝具の匠ステージ
寝具のステージでは、掛布団の歴史を辿りながら、掛布団づくりの実演が披露されたよ。布団に使われる木綿の綿(わた)は吸水性と保温性に優れ、蒸れることなく快適。弾力性があって、日に干すと膨らむ性質があり、蒲団としては最高の素材なんだ。木綿の綿が掛布団に使われるようになったのは、戦国時代。それ以前は、自分が着ている着物を掛けて寝ていたそうだよ。その後、綿花の生産量が増えたことで、着物の中に綿を入れると温かいことから生まれたのが掛布団なんだ。首元から肩まですっぽり入る着物の形をしていて、「かい巻き布団」とも呼ばれ、冷気が入らず、とても温かいよ。かい巻き布団は、寝具技能士1級の実技課題にもなっているんだ。

丁寧な綿入れで、ふっかふか
昔は布団が高価だったので、庶民の手には入らなかったんだ。でも、明治期になって、インドから安価な綿が入ってきたことで広まったよ。それでも貴重なものなので、綿を打ち直し、一生ものとして大事に使う文化が生まれたんだ。ステージでは、掛け布団の製作工程が紹介されたよ。幅1m/長さ2m弱のシート上の綿を広げ、側生地に沿って折り曲げ、縦と横に交互に何層も重ね合わせながら、厚みを出していくんだ。この「台張り」の作業が、ふっくらとした心地よい掛布団を作るのに欠かせないんだって。綿づくりが終わったら、側生地の角までしっかり詰めていくよ。綿を入れた開口部を閉じ、綿を側生地に留める「くけ縫い」をしたら、中綿を側生地と馴染ませる「のしつけ作業」で、形を整えていくんだ。丁寧に綿を伸ばし、しっかり落ち着かせて完成。木綿は、天日干しできる唯一の繊維。寝汗は裏地に吸収されるので、干す時は、裏地を日光に当てるといいんだ。お日様に干した木綿の掛布団は、気持ちよさそうだね。

縁なし畳の今と昔〜畳の匠ステージ
ステージでは、今と昔の素材を使い分け、畳職人による縁なし畳の製作が披露されたよ。昔は縁なし畳が主流で、畳替えがなかなかできなかったから、畳表には丈夫な草を使ったそうだよ。織ったり縫ったりする作業が大変で、経験を積まないと上手にできないそうだよ。通常は半日ほど水に浸し、柔らかくしてから包丁を当て、裏から指で折り目をつけていくんだ。包丁を引くと切れ、傷がつくと裂けてしまうので、指の腹で持ち上げるようにして、丁寧に折り目をつけていくよ。この時の力加減に経験の差が出るんだ。匠は筋目をきっちりつけながら折り目を入れ、とてもきれいに仕上げていくよ。良い例と悪い例の実演で、技術の差がよくわかったよ。

時代とともに変化してきた畳づくり
大分県国東市で栽培されている太くて丈夫な「七島い草(しちとういぐさ」と麻糸で編んだ耐久性の高い畳表「琉球表(りゅうきゅうおもて」も紹介されたよ。七島い草は、断面が三角形で太いため、強度と耐火性に優れ、昔は、商家の人の出入りが激しい場所で使われ、普通のい草は、住まいの畳に使われたんだ。この琉球表を使用したのが「琉球畳」だよ。最近の縁なし畳は、藁床ではなく、化学床が主流。藁床は手作業だから手間がかかり、1日3枚くらいしか作れないんだって。藁床は、い草の間に針を通して糸を強く引っ張り、表の藁を締めて、たるみが出ないようにするよ。でも、芯にボードを使う化学床の場合、糸が抜けてしまうので、機械で均一に仕上げるんだって。時代の変化とともに建物や暮らしのあり方が変わり、畳づくりも変化してきたんだね。
匠たちが長年磨き上げてきた技を披露した、3日間のスペシャルステージ。どれも見応えがあって、間近で実演を体感することで、匠の技の凄さや奥深さを知ることができたよ。
 #TOKYOものづくり部
#TOKYOものづくり部



 #110
#110 #109
#109 #108
#108 #106
#106 #105
#105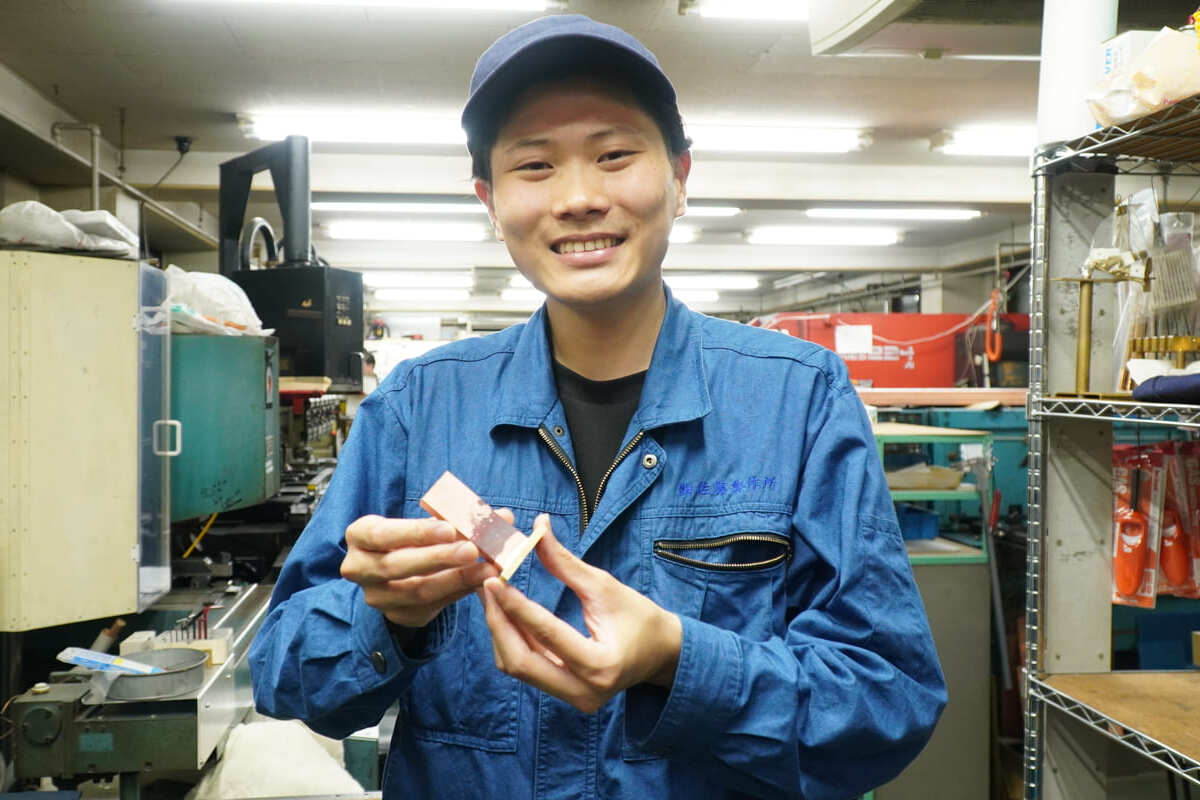 #104
#104 #103
#103





